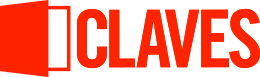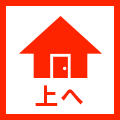

こんにちは!クラベス採用担当の東野です。
クラベスでは、入社半年後に「Member's Entry」という自己紹介記事を書いてもらっています。これから挑戦してみたいことなどを紹介してもらっているのですが、「入社してからの活躍を知りたい!」という声を多数いただきました。
そこで、入社から数年経ったメンバーの活躍を紹介するインタビュー企画を始めることになりました!
今回は、入社から4年半のエンジニア 遠藤さんをご紹介します。

遠藤さんは現在、クラベスの自社サービス事業を推進するための体制設計や制度づくりに携わっています。開発プロジェクトでは、アーキテクチャなど設計のレビューを通じて、品質の向上やゴールに向かうサポートをする役割を担っています。
この記事では、「これどう実現するの?」という状態から形を作り上げる遠藤さんの仕事、AI時代でも変わらない「考える力」の重要性、そして革新的なサービスを作り続けるというキャリアの軸をご紹介します!
入社1年の自己紹介はこちら
自社サービス出身の私が、スピード感を求めて受託の会社に入った理由

ゼロから作る、自社サービスの土台
遠藤さんが現在取り組んでいるのは、自社サービスの体制設計です。
「現在は、特定のプロジェクトに入っているわけではなくて、自社サービスの体制構築に取り組んでいます。制度設計や目的の明確化、開発フェーズの定義などを考えています」
会社として自社サービスを進めていきたいけれど、実際、どう動けばいいのか分からない。そうした課題に対して、制度や目的、判断基準を整理して、メンバーが迷わず動けるための環境を作っています。
「他にも、社内の進行中プロジェクトのレビューやサポートをしています。設計や実装のレビューですね。環境に関する相談を受けることもあります。」
「これどうやるの?」から形に落とし込む
遠藤さんの本領が発揮されるのは、混沌とした状態から形を作り上げる瞬間だと言います。
「具体的な業務でテンションが上がったり下がったりすることはあまりなくて、むしろ『これ、どうやるの?』というカオスな状態から形に落とし込み、実現することに興味があるんです」
例えば、とあるプロジェクトに参画したときの話。
開発フェーズに入った段階で、遠藤さんはインフラ担当となりました。引き継がれた設計資料を見ると、バッチの情報はAWS Lambda アイコン、たった1つだけ。
この時ばかりは、「バッチって何があるんだろう。さすがに情報が少なすぎる」 と、思わず突っ込んだそうです。

本来、バッチ処理には
・何をトリガーに動くのか ・どのリソースにアクセスするのか ・前後の処理は何か ・時間の制約はあるのか
考えるべきことはたくさんあります。
「情報を整理しながら、具体的な処理内容や環境要件を洗い出していきました。エンジニアの仕事は、抽象を具体化することだと思っています」
ゴールが明確でなくても、遠藤さんは形を作っていけます。
「目の前のできることから積み上げて整理していく中で、ゴールを探っていくアプローチを採っています。最終的にものを作るのがエンジニアの仕事ですし、成果をつなげるためには必要なことだと思ってます」
このアプローチは、現在取り組んでいる新規事業の立ち上げでも同様です。
「他者の事例やフレームワークを参考にしながら、具体的な形を固めていきます。新規事業に関するインプットのために、最近は関連する本を読むことが多いですね。
普段は本を読むことよりも自分でものを作って学ぶことが多いんですけど、いまは新規事業に必要な知識の習得に時間を割いてます」
ビジネスゲーム新規開発PJの成功体験

これまでのプロジェクトで印象的なエピソードを聞いてみました。
「ビジネスゲームの新規開発プロジェクトかなと思います。元々オフラインで開催していた研修をオンライン化するというプロジェクトでした」
オフラインでは、シートでスコアデータを管理していました。しかし、オンライン化にあたって、このデータをどう扱うべきかが課題となりました。一般的には、データベースを構築してデータを移行する方法が考えられます。
しかし、遠藤さんは別のアプローチを選びました。
「データの持ち方をデータベース以外も活用して工夫することで、多様なビジネスゲームに汎用的に応用できるようになり、よりニーズにあったビジネスゲームを提供できるようになりました。抽象的なものを具体的な形にして、実際に動くものにできた時の達成感は大きかったですね」
AI時代でも変わらない、エンジニアの本質
遠藤さんが仕事で一番大切にしていること、それは「なぜに答える」こと。
「自社サービスの制度設計や運用、アーキテクチャの選択、コードの記述など、あらゆる決定に対して『なぜそうしたのか』を説明できることが大事だと思ってます」
この思考スタイルは、大学院時代の研究で培われたそう。

「研究では常に『なぜ』が問われるんです。なぜAなのか、Bではダメなのか。提案する内容すべてに根拠が求められる環境でした」
そして今、AI時代においてこの力の重要性を実感しています。
「AIが発展した現代では見かけの品質が向上しても、中身が実現可能かを検証することや、深く考えることの重要性が増していると思います。中身が実現するものなのかを考えて、検証しないといけない。この辺はAIが苦手とする部分ですね」
技術が進化しても、「考える力」の重要性は変わりません。
革新的なサービスを作り続けたい
「革新的なサービスを作り続けたい」 それが遠藤さんの学生時代からの軸です。
「学生時代からプロトタイプを制作したり、不便を感じたときに個人でアプリをつくったり。サービスを通して世の中を便利にすることに軸足を置いてきました」
クラベスのビジョンとも通ずるこの目標。今、遠藤さんが求めているのは新しい挑戦です。
「認証認可やポイント基盤は、ある程度社内でもノウハウがたまって、やり方が確立されつつあります。新しい領域で、何か考えて作れるところはないかなと思っています」

確立された技術よりも、未知の領域。 考える要素が多いプロジェクト。
そんな環境が、遠藤さんのエンジニア心をくすぐると言います。 そして、クラベスにはその挑戦ができる環境があります。
遠藤さんに魅力を伺うと、「端的に言えば自由度ですね」と教えてくれました。
働き方、役割、制度づくり、サービス設計。 あらゆる面で裁量があり、チャレンジできる環境。 フレックス、フルリモート。 技術領域を広げることも、新しい役割に挑戦することも。
自分がどう働くか、どう成長するかを、自分で決められる環境が魅力的だと、お話してくれました。
あるべき姿を、一緒に考える
最後に、遠藤さんはこう語ります。
「あるべき姿を考えられる人と一緒に働きたい」
ゴールが見えていなくても、手探りで進めていかなければいけない状況はあります。そんな中でも、「こうであれば最善なんじゃないか」と考えて、その理由を説明できる。そんな人と働きたいと話してくれました。
エンジニアリングの本質。 それは、「考える」こと。
カオスを整理し、抽象を具体化する。「なぜそうするのか」に答えられる力こそ、AI時代に求められる本当のエンジニアの価値です。
遠藤さんの挑戦は、これからも続きます。
クラベスは、「システム開発のあるべき姿を目指す」に共感するエンジニアが集まり、本当に価値あるものを提供するために「なぜそうするのか」を一人ひとりが考え、この想いを大切にしています。
この価値観に強く共感し、共に成長し合いながら、いいものを創っていきたいと本気で思える仲間を、私たちは探し続けています。